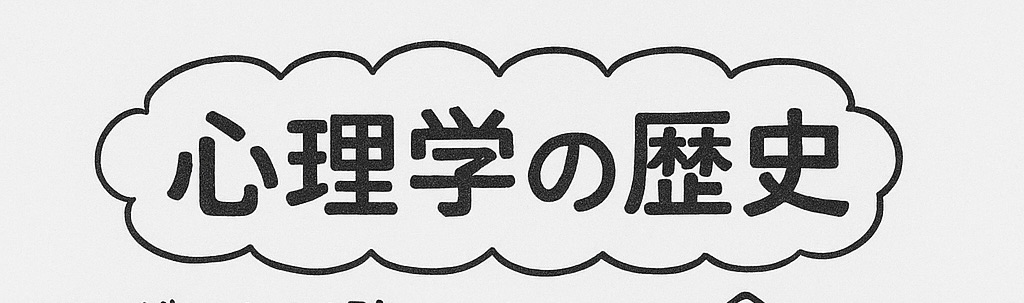- ヴント以降目覚ましい進歩を遂げた心理学
心理学が学問として成立したのは、ドイツのライプチヒ大学、哲学教授ヴントの学説からでした。彼は1879年、大学に心理学実験室を作り、哲学の主観的な手法を捨てて、自然科学の実験方法を取り入れ、心を科学的に探究することを目指したのです。これが、ヴントが現代の「心理学の父」と呼ばれる所以です。
ヴントの学説とはこのようなものでした。彼は、人の心にはいくつもの「心的要素」があり、これが結合することで、「心的要素の結合体」が形成されるとしたのです。わかりやすく言うとこうです。まず「みかん」という言葉から連想するものを思い浮かべてみてください。視覚からは「オレンジ色」「丸い」、味覚からは「甘い」「酸っぱい」、嗅覚から「芳しい」、触覚からは「冷たい」「すべすべだ」などの概念が、いくつも出てくるでしょう。これら、人の五感が刺激されることによって現れた概念が、「心的要素」のひとつひとつです。そしてこれらが結合して「みかん」という心的要素の結合体が成立したというわけです。
つまり、こういった結合の法則を解明することで、人の心の動きを探ることができるというのがヴントの考えというわけです。単に自分の心を見つめ、意識を観察する哲学とは違い、意識を構成している要素を取り出し、分析する点が大きな特徴と言えるでしょう。この分析方法から、ヴントの学説は「構成主義」と言われています。
⸻
- 心理学のあけぼの 紀元前〜17世紀
それではヴント以前の心理学はどのようなものであったのでしょう。実は、人間の心を論理的に考えようとしたのは、古代ギリシャの哲学者アリストテレスだと言われています。
彼は著書『霊魂論』の中で、感覚、記憶と想起、睡眠と覚醒など、現代の心理学にも通じるテーマを論じています。
しかし、アリストテレスのこの哲学的心理学は、継承する人が現れず、そのままの状態で過ぎ去りました。再び心理学的考察が行われるようになったのは、実に、16世紀後半のルネサンス期になってからです。
さらに17世紀半ばには、イギリスで経験主義心理学が生まれ、やがてロックやヒュー ムらに提唱された『連想心理学』へと発展していきます。
同じ頃ドイツでは理性主義心理学が生まれ、デカルト、ヴォルフらによって提唱され た『能力心理学』へと発展しました。
ちなみにこの2つの心理学は、「人は生まれながらに才能を備えているか」という点 において対照的な見解を出しており、前者の「連想心理学」は、人は生まれた時は白紙 で、連想によって感覚と観念が結びつき、やがてまとまった観念体系が形成されるとし ています。対する「能力心理学」は、人は生まれながらに決まった能力や才能があると し、精神構造を知・情・意の3つに分け分析する方法をとっていました。