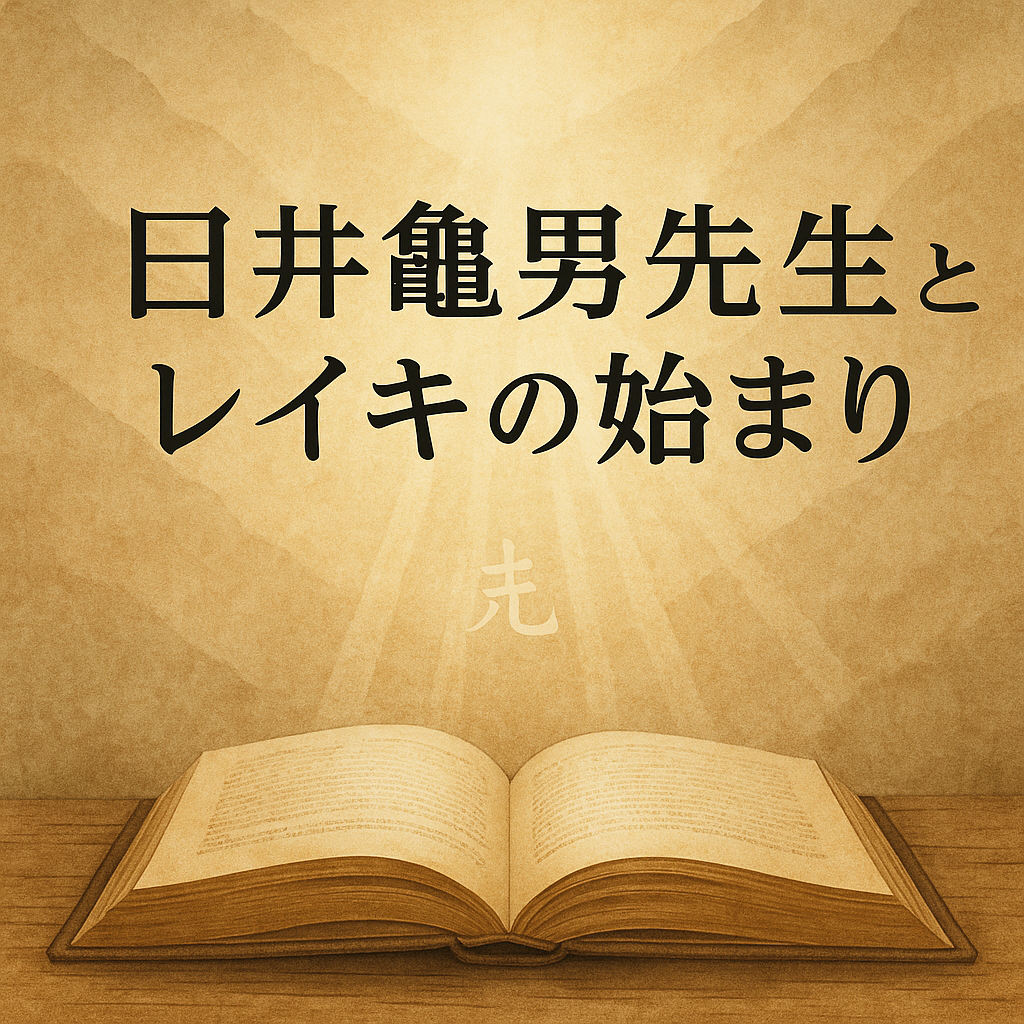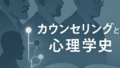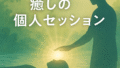はじめに
レイキを学ぶ上で欠かせないのが、その創始者である 臼井甕男(うすい みかお)先生 の存在です。レイキの技法や理念は、臼井先生の探求心と体験から生まれました。レイキレベル1では、手当てによる癒しの実践と並んで、この創始者の歩みや思想を知ることが学びの土台になります。今回は臼井先生の生涯とレイキ法誕生の背景を振り返り、私たちが学ぶ意味を考えてみましょう。
⸻
臼井甕男先生の生い立ち
臼井甕男先生は1865年(慶応元年)、岐阜県山県郡谷合村(現・岐阜県山県市)に生まれました。幼少期から学問に励み、仏教や医学、心理学、さらには宗教的思想にも関心を持ちました。当時の日本は明治維新を経て大きく変革していく時代であり、臼井先生も新しい知識を吸収しながら、人生の意味を探求していったと伝えられています。
若い頃から「人の苦しみをどう癒すか」「人生をよりよく生きるにはどうすべきか」という問いを抱え、さまざまな分野を学び歩いたことが、後のレイキ法創始につながっていきました。
⸻
レイキ誕生のきっかけ
臼井先生がレイキを体得したのは1922年のことです。長年の修行と探求の末、京都・鞍馬山で21日間の断食瞑想に入られました。最終日、強烈な光に包まれるような体験を経て、宇宙生命エネルギーと一体になる感覚を得たとされています。この体験が「霊気法」の出発点でした。
山を降りた臼井先生は、道端で足を怪我した際に思わず手を当てたところ、痛みが和らいだと伝えられています。これが「手当て療法」としてのレイキ法の最初の実践例とされ、やがて人々に広めていく契機となりました。
⸻
臼井霊気療法学会の設立
1922年4月、臼井先生は東京・青山原宿に「臼井霊気療法学会」を設立しました。ここでレイキを人々に伝え、心身を癒す実践を指導しました。レイキは宗教ではなく、誰でも学べる普遍的な癒しの方法として位置づけられ、多くの人々が臼井先生のもとを訪れました。
学会では「手当てによる療法」だけでなく、日常生活の心構えとして「五戒」を説きました。これは「今日だけは 怒るな 心配すな 感謝して 業をはげめ 人に親切に」というシンプルながら深い教えで、心の持ち方を整えるための実践指針となっています。
⸻
レイキ法の理念
臼井先生のレイキ法は、単なる病気治しの技術ではなく、人間の心身を調和させ、よりよく生きるための「生活法」でした。
• 自然との調和:宇宙のエネルギーと共鳴し、人間本来の生命力を取り戻す。
• 心身一如:心と体を切り離さず、両方を整えることで健康を目指す。
• 普遍性:誰にでも習得可能で、宗教や文化に関わらず実践できる。
これらの理念は、現代においてもレイキが多くの人々に支持され続ける理由となっています。
⸻
臼井先生の晩年と遺産
臼井甕男先生は1926年(大正15年)に享年62歳でこの世を去りました。晩年には関西や広島方面へも赴き、レイキ法を広める活動を続けていたと伝えられています。
先生の死後も、弟子たちによってレイキは国内外へと広がり、現在では世界中で数百万人以上が実践しているといわれています。臼井先生の探求心と実践は、時代を超えて多くの人々の心身を癒し続けているのです。
⸻
レイキレベル1で臼井先生を学ぶ意義
レベル1(初伝)では、手当てによるセルフヒーリングや基本的な実践方法を学びますが、その根底には臼井先生の理念があります。
• なぜ手を当てるだけで癒しが起こるのか
• 人が健やかに生きるために必要な心のあり方とは何か
• 学んだ技法をどのように日常生活で活かすか
これらを考えるとき、創始者の歩みを知ることはとても大切です。臼井先生が歩んだ道を理解することで、単なる技術ではなく「生き方」としてのレイキを学ぶことができます。
⸻
まとめ
レイキの創始者・臼井甕男先生は、人々の苦しみを癒す方法を求めて生涯をかけて探求しました。その結果として生まれた「レイキ法」は、今もなお世界中で実践され、多くの人の心身を支えています。
レイキレベル1で臼井先生の生涯を学ぶことは、私たち自身が「なぜレイキを学ぶのか」を見つめ直す大切な機会です。単なる癒しの手法を超え、人としての在り方を考える学びとして、臼井先生の教えを心に刻んでいきましょう。